人材不足や労働環境改善のため、自律走行ロボットを導入する企業が増えています。しかし、実際に自律走行ロボットを導入しようとしても、そもそも自律走行ロボットはどのようなものかがわからず、困っている人も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、自律走行ロボットの現状と国の動きについて解説します。自律走行ロボットの活用事例も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
SLAMとは
SLAMとは、「Simultaneous Localization and Mapping」の略で、「自己位置推定と環境地図作成を同時に行う」技術のこと。

ロボットがカメラやセンサーなどで周囲の環境を観測することで自分の位置を推定し、同時に地図を作成します。移動するたびに自分の位置を更新しながら地図を更新することで、未知の環境であっても自律的に走行することが可能です。
本項目では、SLAMを活用した「自律走行ロボット」について解説します。
自律走行ロボットとは
自律走行ロボットとは、本体に搭載されたカメラや各種センサー、GPS情報などをもとに周囲の環境を検知し、自律的に目的地へ移動するロボットのこと。走行には、磁気のガイドテープのような誘導体を必要としません。
- ・2次元SLAM方式
- ・画像処理と3Dモデル比較方式
- ・3次元SLAM方式
これらのSLAM 技術の活用により、大きな現場のレイアウト変更をせずにロボットの導入が可能です。
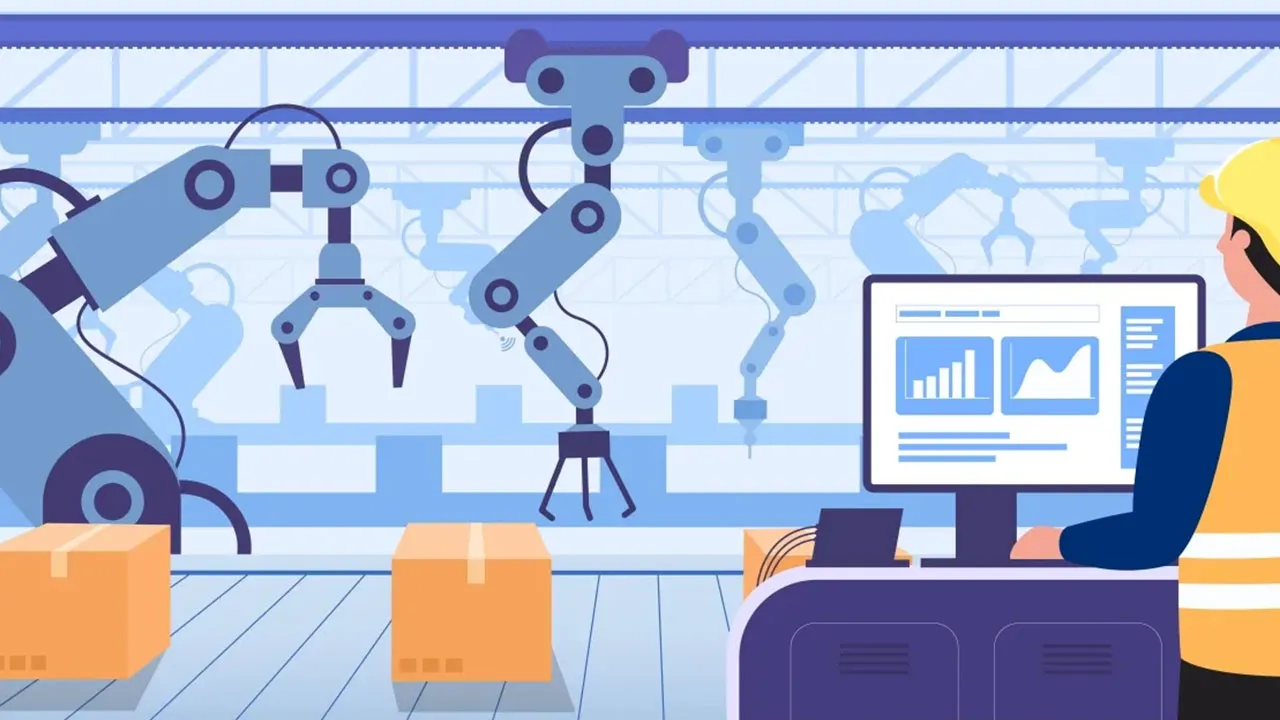
2次元SLAM方式とは
2次元SLAM方式では、レーザースキャナで計算した複数の距離データで地図を作成し、地図と距離データを照合することで、自分の位置を推定します。レーザー照射の跳ね返り時間を計算するため、周囲の明るさに関係なく、データの取得が可能です。ただし、周囲に検出しやすい固定物がないと自己位置の検出が困難だったり、大勢の作業員に取り囲まれると検出を失敗したりするのが難点です。
画像処理と3Dモデル比較方式とは
カメラ画像と3Dモデルデータを比較し、走行ルートを導き出すことで自律的に走行する方式です。無人化ニーズが高い、冷凍倉庫や危険物管理区域での使用が想定されています。実際の状態が3Dモデルデータと異なる状態の場合、検出性能が落ちてしまうことが課題です。
3次元SLAM方式とは
ステレオカメラで撮影した映像から、環境の3次元地図の作成と自己位置や姿勢を推定する方式です。頻繁な環境変化をリアルタイムに把握し、障害物を避けて走行できます。ただし、映像から位置情報などを計算するため、暗い場所や明暗差の激しい場所での精度の低下が課題です。
自律走行ロボットが活躍する使用例
SLAM技術を採用した自律走行ロボットは、周囲の環境を把握し、自律的に行動できるため、さまざまなシーンで活躍しています。
本項目では、自律走行ロボットが活躍する事例として、「物流センター」と「スーパーマーケット」、「デリバリーロボット(ラストワンマイル)」を紹介します。
物流センター
物流センターでは、AMR(自律型協働ロボット)が、パレットやその他の大きな荷物の積み下ろし、運搬、積み重ね、取り出しなどで活躍しています。たとえば、ピッキング作業の効率化も可能です。AMRがピッキング作業における歩行の大半を人に代わって行うことで、従業員はピッキング作業に集中できます。具体的には、複数のAMRがピッキングする商品の位置に移動し、従業員は近くのAMRの画面指示に従ってピッキング作業を行います。作業終了後、従業員は近くにある別のAMRの場所へ移動して次の作業を行い、AMRは別のピッキング商品の位置に移動したり、梱包場所へ移動したりするといった流れです。従業員は、商品を探すために歩き回る必要がなく、必要最小限の移動でピッキング作業を行えます。さらに、ピッキングに集中することでミスも減らせるため、従業員の負担軽減と生産性向上を実現可能です。
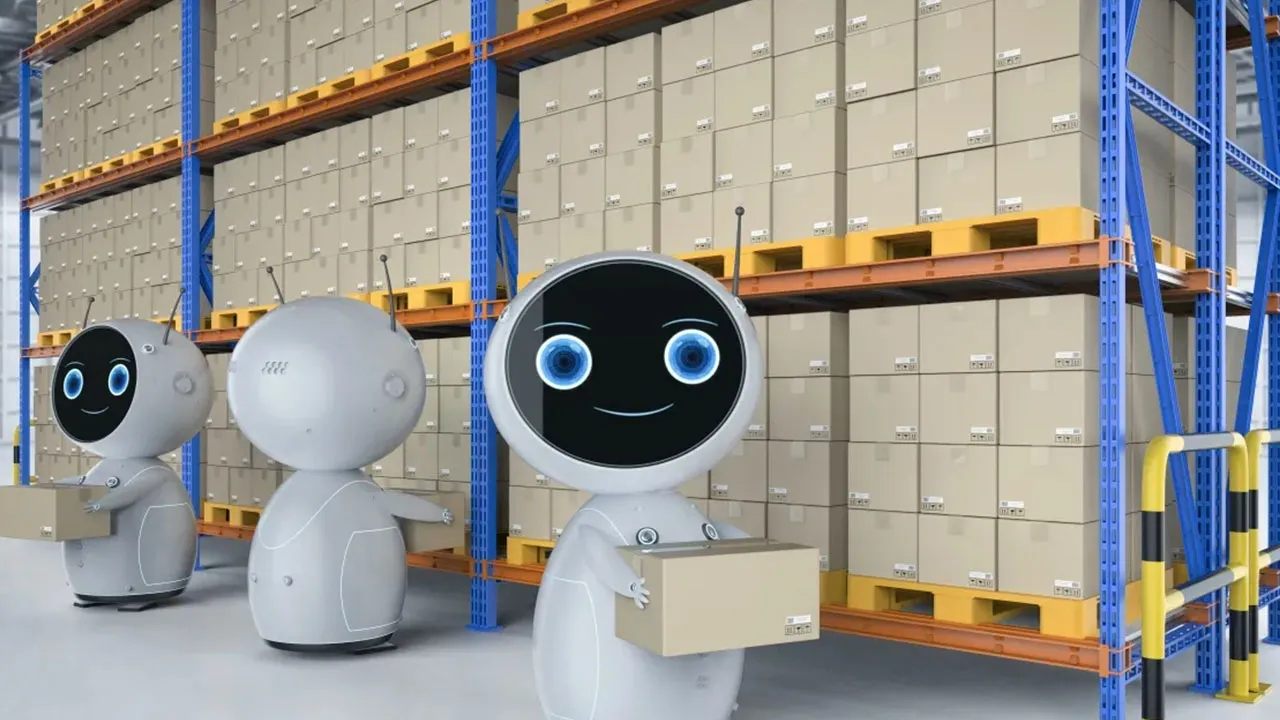
スーパーマーケット
スーパーマーケットにおいても、ネットスーパー向けのピッキング支援にAMRが活用されています。ピッキング担当者の作業効率の向上とミスの低減、わずかなトレーニング時間での作業習熟といった効果を実現しています。カメラやセンサーからリアルタイムに位置情報を取得し、自律走行が可能です。海外では、薄型高精度のインホイールモーターを開発することで、狭い通路で安全に自律走行が可能なAMRの製品化なども実現しています。
デリバリーロボット(ラストワンマイル)
ラストワンマイルとは顧客へ商品が届くまでの最後の区間のことで、具体的には営業所から自宅・店舗などです。海外では、ラストワンマイル配送の代替補助手段として、自動走行ロボットによる配送が社会実装され始めています。ECの発達や人手不足により、効率化実現が急務となっている国内物流業界においても、自動走行ロボットへのニーズが高まっており、日本郵便などの多くの事業者が実証実験を開始しています。日本郵便では、ドローンと配送ロボットが連携した荷物配送実験や、配送ロボットによるオフィスビル内配送などを実施。人手不足解消や生産性向上などが期待されています。
自動配送ロボットの実装に向けて日本はどのように動いているか
本項目では、自動配送ロボット実装に向けた日本の動きを「法案の改正」と「業界団体の動き」に分けて紹介します。
法案の改正
日本国内では、2022年4月に低速・小型の自動配送ロボットの公道走行などのルールを定めた「道路交通法の一部を改正する法律」が成立しました。遠隔操作により通行する車で、最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当するものを「遠隔操作型小型車(自動配送ロボット等)」とし、歩行者同様の交通ルールを適用する、としており、2023年4月までに施行予定です。公道による実証実験も北海道更別村や茨城県つくば市、神奈川県藤沢市などで行われており、社会実装段階が近づいています。
業界団体における動き
業界団体の動きとしては、一般社団法人ロボットデリバリー協会で、安全基準とガイドラインの策定、認証の仕組みの構築といった、改正法施行に向けた活動が進められています。また、ロボットデリバリー協会では国際標準化に関する活動も行われており、経済産業省は、「当該市場における我が国企業の国際競争力を高めることにつながり、非常に重要である」と評価しています。
建設現場で自律走行ロボットを導入するならSUPPOTがおすすめ
建設現場で、自律走行ロボットを導入するなら「SUPPOT」がおすすめです。
SUPPOTは、建設現場の資材運搬作業をサポートする作業支援ロボットをレンタルできるサービスです。SUPPOTでは遠隔操縦と作業者の自動追従や2D自動運転、最大100kgまでの重量物積載、悪路・傾斜の走行などが可能なロボットを用意。レンタルなので、購入よりも低コストで導入できる点も魅力です。たとえば、コンクリート運搬をロボットで行うことにより、作業負担軽減と安全性向上、作業効率向上を実現した事例や照明器具を積載したロボットを作業者に自動追従させ、点検業務の効率化・省人化を実現した事例などがあります。
建設現場での資材運搬の効率化や作業者の負担軽減、安全性向上などにお悩みの方は、作業支援ロボットレンタルサービス「SUPPOT」の導入をご検討ください。

まとめ
自律走行ロボットの現状について紹介しました。自律走行ロボットは、既に様々な業界に導入されており、人手不足解消や生産性向上に役立っています。
さらに2023年4月の改正法施行による、国内の自動配送ロボットの社会実装が近づいているなど、社会としても自律走行ロボットの活用を後押ししている状況です。人材不足や労働環境などに課題を抱えている企業は、自律走行ロボットの導入を検討してみてはいかがでしょうか。「ロボットの種類がさまざまで、どれを選んでいいのかわからない」、という方におすすめなのが、作業支援ロボット「SUPPOT」レンタルサービスの利用です。
SUPPOTは1ヶ月からレンタル可能なサービスなので、初期費用もかからず無駄なく利用できます。さらにレンタル利用後は電話サポート、保険付帯、故障時即代替対応などのサポートを受けられるので、ロボット初心者の方でも安心して利用可能です。SUPPOTの導入により重い荷物の運搬作業を削減できるため、人件費や労働コストの軽減、生産性の向上などに繋げることができます。SUPPOTの利用を検討されている方は、ぜひ運営会社であるソミックトランスフォーメーションへお問い合わせください。
参考文献
第6回 自動走行ロボットを活用した配送の実現に向けた官民協議会 議事要旨|経済産業省https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/jidosoko_robot/pdf/006_gijiyoshi.pdf
第6回 自動走行ロボットを活用した配送の実現に向けた官民協議会|経済産業省https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/jidosoko_robot/006.html

