建設業界は他の業界よりも高齢化が著しく、中長期的な担い手不足が課題です。そのため、DXによって業界の仕事の仕方やビジネスそのものを変革させることを迫られています。
本記事では、建設業界におけるDXについて解説します。建設DXとはどういうことか、建設業界の抱える課題などについても紹介するので、人手不足や従業員の長時間労働などにお悩みの方は、ぜひご覧ください。
「建設DX」とは
建設DXとは、デジタル技術によって建設業の業務や組織などを変革させることです。建設DXにより業界全体の生産性を向上させ、労働力不足をはじめとする業界の課題解決に対応することが期待されています。
本項目では、建設業界におけるDXについて紹介します。
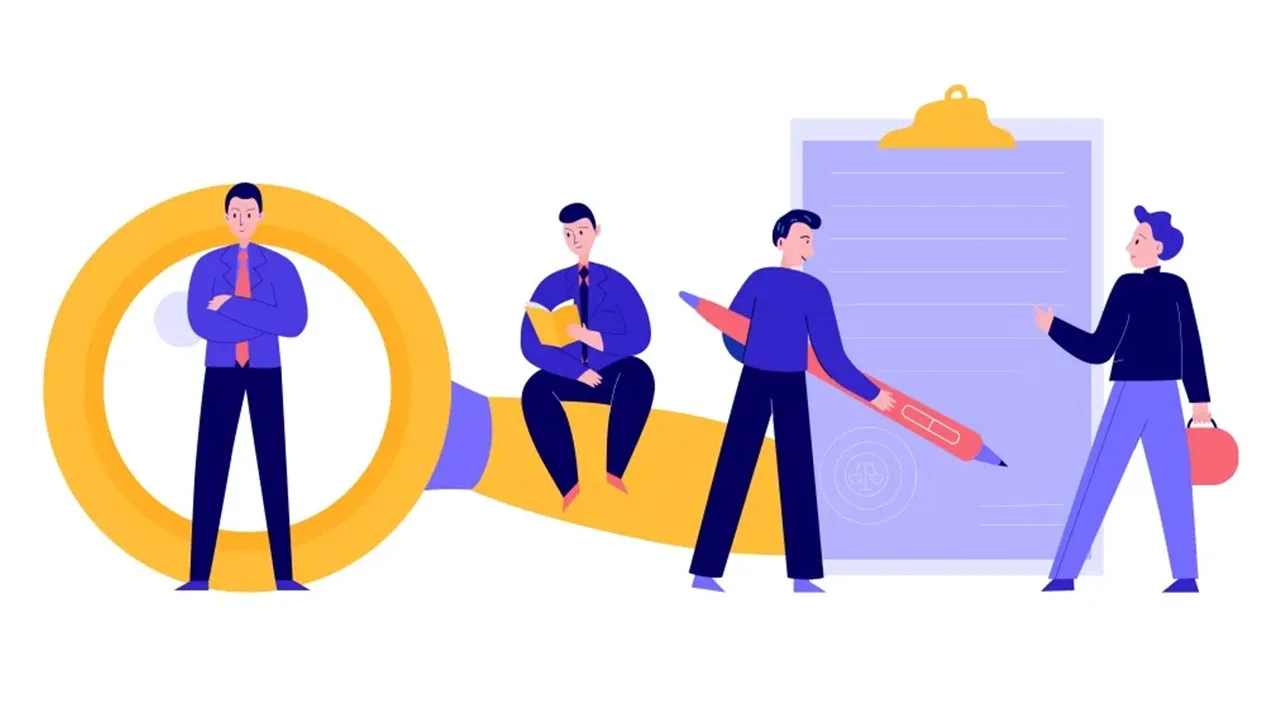
建設業界におけるDX
DXとは、Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)の略称。経済産業省の「デジタルガバナンスコード2.0」では、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。」と定義しています。とりわけ、建設業界はDXが急務。デジタル技術を取り入れることで、業務プロセスの改善や最適化を行い、人手不足や長時間労働などの建設業界が抱えるさまざまな課題の解決と、業務や組織の変革が期待されています。
建設業の3つの課題
建設業における代表的な課題としては、下記の3つが挙げられます。
- ・労働現場の危険性
- ・労働時間の長さ
- ・人材不足
DXには、これらの課題への対応が求められています。それぞれの課題について、詳しく紹介するので、ぜひご覧ください。
労働現場の危険性
建設現場は、危険な環境での作業が多いことや重機をはじめとする危険な道具で作業することが多いこともあり、他の産業と比べて労働災害は多い傾向です。建設業労働災害防止協会によると、令和3年の死傷者数は16,079人(全産業の10.7%)、死亡者数は288人(同33.2%)となっています。総務省統計局の「令和3年労働力調査年報」によると、主な産業別就業者数・雇用者数のうち建設業が占める割合は約7.2%。就業者数の割合と死傷者数や死亡者数に占める割合を比較すると、建設業の労働現場の危険性は高いと言えるでしょう。

労働時間の長さ
労働時間の長さも建設業が抱える課題の1つです。厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和4年分結果確報」によると、建設業の月間労働時間は、163.5時間。調査産業計の136.1時間と比べて27.4時間も多くなっています。さらに建設業の月間出勤日数は20.0日。調査産業計の17.6日と比べて、2.4日も多い結果です。単純に12ヶ月分となると、28.8日も多く、約1ヶ月も多く働いていることになります。これらは建設現場において週休2日制がまだ十分に定着していないことが原因と考えられ、労働時間の長さは従業員の疲労の蓄積や怪我などにつながるでしょう。
人材不足
建設業就業者の高齢化進行による、人材不足も大きな課題です。総務省の「労働力調査」によると、建設業就業者は2021年には55歳以上が約35%、29歳以下が12%となっており、高齢化が著しく進行しています。55歳以上の就業者は、10年後には大半が引退するため、若年入植者の確保や育成が急務です。建設業界は高度成長期やバブル期に建てられた建物の老朽による維持管理や再建需要、さらに大阪万博やリニア中央新幹線などの大規模建設需要が見込まれるため、人材不足を改善できないと、大きな需給ギャップが生まれてしまいます。
建設DXの鍵を握る「BIM/CIM」
建設DXの鍵を握るとされている「BIM/CIM」についてご存知でしょうか。BIM/CIMは建設業におけるシステムの効率化・高度化を図る取り組み。2023年度から小規模を除くすべての公共事業で、BIM/CIMの原則適用が始まります。
本項目では「BIM/CIM」について、そのメリットや現在の状況、今後の展望について紹介します。

BIM/CIMとは?またそのメリット
BIM/CIMとは、一連の建設生産・管理システムの効率化・高度化を図る取り組みのこと。計画、調査、設計段階から、3次元モデルを導入することで、その後の施工や維持管理のフェーズにおいても、事業全体にわたる関係者の情報共有が容易になります。BIM/CIMにより、ミスや手戻りの大幅な減少、工期短縮等による安全性の向上や生産性の向上、副次的案効果として建設業界に従事する人のモチベーションアップなどがメリットとして期待されています。また、建設DXで活用が期待されているARや遠隔検査、重機の自動制御などは、設計データや関連データなどが必須です。そのため、建設プロセスを一貫して管理できるBIM/CIMが、建設DXを促進する根幹と言えます。
状況と今後の検討について
国土交通省は2020年4月に、2023年度からのBIM/CIMの原則適用を発表。小規模を除くすべての公共事業で、BIM/CIMの原則適用が開始されます。国土交通省の「第6回 BIM/CIM推進委員会『これまでの取組への対応について』」によると、2020年度のBIM/CIM活用実績は515件。BIM/CIM原則適用により、中小規模の企業を含めた裾野の拡大と、建設生産・管理システムの効率化を目指すとしています。
建設現場でロボットを導入するならSUPPOTがおすすめ
建設現場で、自律走行ロボットを導入するなら「SUPPOT」がおすすめです。
SUPPOTは、建設現場の資材運搬作業をサポートする作業支援ロボットをレンタルできるサービスです。SUPPOTでは遠隔操縦と作業者の自動追従や2D自動運転、最大100kgまでの重量物積載、悪路・傾斜の走行などが可能なロボットを用意。レンタルなので、購入よりも低コストで導入できる点も魅力です。
たとえば、コンクリート運搬をロボットで行うことにより、作業負担軽減と安全性向上、作業効率向上を実現した事例や照明器具を積載したロボットを作業者に自動追従させ、点検業務の効率化・省人化を実現した事例などがあります。建設現場での資材運搬の効率化や作業者の負担軽減、安全性向上などにお悩みの方は、作業支援ロボットレンタルサービス「SUPPOT」の導入をご検討ください。

まとめ
建設業界は他の業界と比べて高齢化が進行しており、次世代の担い手不足が長年の課題です。建設DXにより、業界の仕事の仕方や組織のあり方などを変革し、課題へと対応することが求められています。中でも「BIM/CIM」は、建設DXを促進する根幹として期待されており、2023年度から原則適用が開始されます。
建設DXへの取り組みを行っている企業も少なくありません。中でもロボットの導入については、建設現場での人材不足や労働環境改善に対する効果が期待できます。 人材不足や労働環境などに課題を抱えている企業は、簡単な作業からでも、ロボットの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
「ロボットの種類がさまざまで、どれを選んでいいのかわからない」、という方におすすめなのが、作業支援ロボット「SUPPOT」レンタルサービスの利用です。 SUPPOTは1ヶ月からレンタル可能なサービスなので、初期費用もかからず無駄なく利用できます。さらにレンタル利用後は電話サポート、保険付帯、故障時即代替対応などのサポートを受けられるので、ロボット初心者の方でも安心して利用可能です。 SUPPOTの導入により重い荷物の運搬作業を削減できるため、人件費や労働コストの軽減、生産性の向上などに繋げることができます。
SUPPOTの利用を検討されている方は、ぜひ運営会社であるソミックトランスフォーメーションへお問い合わせください。
参考文献
国土交通省 第6回 BIM/CIM推進委員会「これまでの取組への対応について」https://www.mlit.go.jp/tec/content/001423080.pdf
BIM/CIMとは:国土交通省https://www.nilim.go.jp/lab/qbg/bimcim/about_bimcim.html
令和5年度以降の検討について:国土交通省https://www.mlit.go.jp/tec/content/001584536.pdf
産業界のデジタルトランスフォーメーション(DX)https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/dx.html
デジタルガバナンス・コード2.0https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dgc/dgc2.pdf
建設業デジタルハンドブックhttps://www.nikkenren.com/publication/handbook/chart6-4/index.html

