遠隔操作ロボットとは、離れた場所から操作できるロボットのことです。製造や物流、農業などの現場で活躍しています。遠隔操作ロボット導入を検討している企業の中には、遠隔操作ロボットにはどんな種類があるのか、実際に遠隔操作ロボットはどう活用すればよいのかなど、お悩みの方も多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、遠隔操作ロボットの種類や遠隔操作ロボットを導入するメリット・デメリットなどを解説します。遠隔操作ロボットの導入を検討されている方は、ぜひご覧ください。
遠隔操作ロボットの種類
遠隔操作ロボットの種類は「マスタースレーブ型」と「コックピット型」の2種類に大別できます。それぞれのタイプで向いている作業が異なるため、遠隔操作ロボット導入の際には、確認が必要です。本項目では「マスタースレーブ型」「コックピット型」それぞれのタイプがどのようなものかを解説します。自社の作業内容で適しているのはどちらか、ぜひ確認ください。
マスタースレーブ型
マスタースレーブ型は、制御・操作を担当するマスター機を使って、制御下にあるスレーブ機を動かすタイプの遠隔操作ロボットです。電気的に接続できていれば操作できるため、無線接続でも操作できます。たとえば、医療分野の手術支援ロボットはマスタースレーブ型です。医師がマスター機を操作し、スレーブ機が連動することで、遠く離れた場所からでも手術ができるようになっています。1つのマスター機で、複数のスレーブ機を制御・操作することもできます。同じ機能の機器をまとめて動かすことができるため、同じ作業を同時に行いたい場合にもぴったりです。
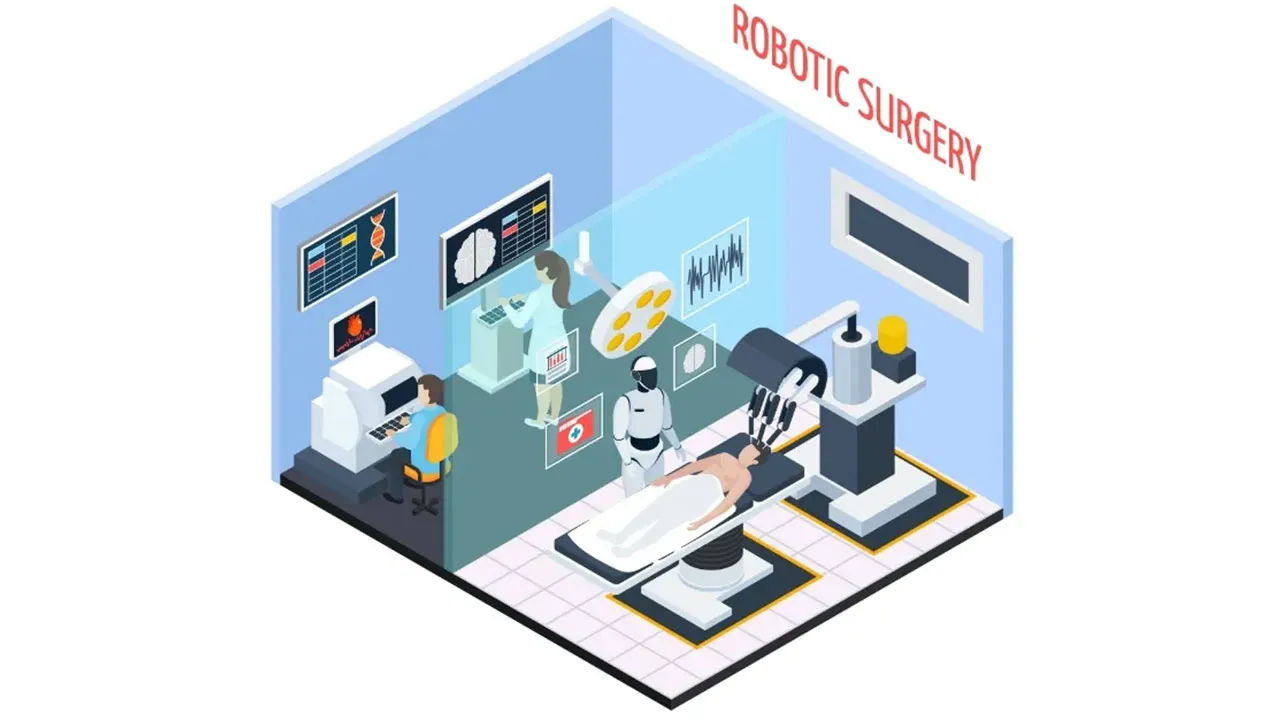
コックピット型
コックピット型は、カメラ映像や各種センサーなどの情報をモニタリングしながら操作するタイプのロボットです。情報をモニタリングしながら操作するため、より現場の情報を把握しながら操作したい場合に向いています。振動や衝撃を体感できるタイプであれば、より臨場感のある操作が可能です。危険を伴う場所での利用に適しており、建設現場や災害現場などでの活躍が期待されています。
業界別における課題は?

遠隔操作ロボットは、建設や物流、農業、医療など、さまざまな業界で導入されており、課題解決に役立てられています。本項目では、「物流現場」「農業現場」「建築土木現場」「製造業」を取り上げ、各業界における課題について解説します。
1.物流現場の課題
物流現場では、「小口配送増加」や「人手不足」が大きな課題となっています。EC通販の普及により、1つの配送先に少量の荷物を届ける「小口配送」が増加傾向です。小口配送は配送回数が増えるため、人件費などがかさんで、物流コストが上がってしまいます。小口配送は再配達になることが多く、ドライバーの負担が増え、労働環境の悪化にもつながっています。日本では少子化による労働人口減少が顕在化しており、物流でも人手不足の企業は少なくありません。新たに人材を確保しようとしても、採用は簡単ではなく、物流業界全体で激務化しています。
2.農業現場の課題
農業の現場では、高齢化等による担い手の減少が課題です。農林水産省の「農林業センサス」によると、自営農業を行う「基幹的農業従事者(個人経営対)」の数は毎年減少を続けており、基幹的農業従事者の年齢も高齢化傾向が続いています。また、年々離農する農家がある一方、新規就農者数は増えていません。毎年一定の新規就農者がいるものの、経営が上手くいかない、地域に馴染めないなどの理由から、離農するケースがあり、なかなか担い手を確保できていないのが現状です。
3.建築土木現場の課題
建築土木現場も、深刻な人手不足が課題です。国土交通省の「建設産業の現状と課題」によると、建設業就労者は55歳以上が約34%、29歳以下が約11%と高齢化が進行しています。10年後には、高齢者層の大半が引退するため、中長期的な担い手確保が急務です。しかし、若年層の入職者が少なく、逆に離職者が多く出てしまっています。今後も労働人口減少が予想されており、技術継承問題も懸念されています。
4.製造業の課題
製造業においても少子高齢化や労働人口の減少などによる人手不足が課題です。厚生労働省の「2022年版 ものづくり白書」によると、製造業の就業者は約20年間で157万人減少、若年就業者数は約121万人減少しており、若手を確保できていません。一方で、高齢就業者数は、約20年間で33万人増加しており、高齢化が徐々に進んでいることがわかります。また、国内の人口減少により、マーケットの縮小も懸念されています。
遠隔操作ロボットを導入するメリット
国内では、人手不足や高齢化が共通の課題となっており、解決に向けてさまざまな取り組みが行われています。遠隔操作ロボットの導入は、課題解決のために有効な取り組みの1つです。本項目では、遠隔操作ロボットを導入するメリットを解説します。
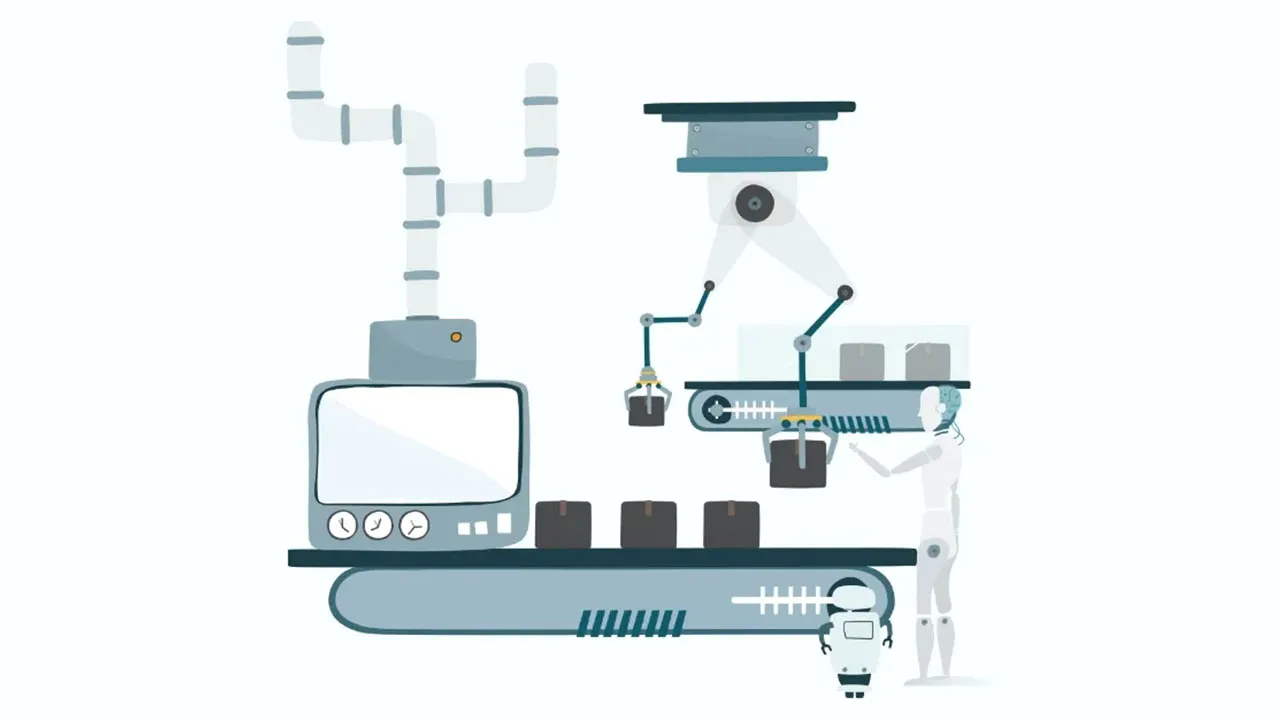
1.省人化が可能
遠隔操作ロボットを導入すると、省人化が期待できます。前述の通り、少子高齢化により、様々な業界で人手不足が深刻です。特に、労働が過酷なイメージのある建設業界では、若手の人材確保が難しくなっています。遠隔操作ロボットを導入すると、同時に複数のロボットを操作できるため、省人化が可能です。また、遠隔操作ロボットを導入すると、これまで力仕事が難しかった従業員でも、現場で働けます。遠隔操作ロボットは定期的なメンテナンスは必要ですが、人間のように過労で倒れることもありません。省人化に取り組みたい企業は、遠隔ロボットの導入がおすすめです。
2.業務効率のアップ
遠隔操作ロボットを導入することで、業務を効率化できます。複数の従業員が1つの工程を進める場合、それぞれコミュニケーションを取りながら業務を進める必要があるため、スムーズに進めるようになるまでに一定の時間が必要です。一方、遠隔操作ロボットは、プログラムにより完璧な連携を取れるため、無駄なく効率的に業務を進められます。人間のように製品の品質がバラつかず、安定するため、歩留まりの改善や生産効率アップも期待できます。業務効率に課題を抱えている企業は、遠隔操作ロボットに置き換えられる工程がないか、検討してみるのがおすすめです。
3.従業員の安全性の確保
高所や災害現場など、危険な場所での作業を遠隔操作ロボットに置き換えることで、従業員の安全性を確保できます。従業員は離れた場所からロボットを操作すれば良いため、危険はありません。また、重い荷物の運搬などを遠隔操作ロボットに任せることで、従業員の体への負担を大きく軽減できます。特に、災害現場や建設現場、製造現場は、危険な場所が多く、労働環境の悪さは若手の入職者が少ない理由の1つです。労働環境改善の意味でも、遠隔操作ロボットの導入をおすすめします。
遠隔操作で走行できるロボットを探しているならSUPPOTがおすすめ
建設現場で、遠隔操作ロボットを導入するなら「SUPPOT」がおすすめです。
SUPPOTは、建設現場の資材運搬作業をサポートする作業支援ロボットをレンタルできるサービス。SUPPOTでは、遠隔操縦や業者の自動追従、2D自動運転、最大100kgまでの重量物積載、悪路・傾斜の走行などが可能なロボットを用意しています。レンタルなので、購入よりも低コストで導入できる点も魅力です。
たとえば、コンクリート運搬をロボットで行うことにより、作業負担軽減と安全性向上、作業効率向上を実現した事例や照明器具を積載したロボットを作業者に自動追従させ、点検業務の効率化・省人化を実現した事例などがあります。
建設現場での資材運搬の効率化や作業者の負担軽減、安全性向上などにお悩みの方は、作業支援ロボットレンタルサービス「SUPPOT」の導入をご検討ください。

まとめ
危険が伴う作業をロボットに任せることで、作業者の安全性を確保できる遠隔操作ロボットについて紹介しました。
日本は少子高齢化による労働人口の減少が大きな課題です。遠隔操作ロボットは、省人化や業務効率の改善、従業員の安全確保といったメリットがあるため、人手不足への対策として期待されています。
遠隔操作ロボトットは、建設や製造、物流、医療など、幅広い業界で活躍しており、タイプもさまざまです。人手不足や労働環境改善に取り組んでいる企業は、簡単な作業からでも、ロボットの導入を検討してみてはいかがでしょうか。「ロボットの種類がさまざまで、どれを選んでいいのかわからない」、という方におすすめなのが、作業支援ロボット「SUPPOT」レンタルサービスの利用です。
SUPPOTは1ヶ月からレンタル可能なサービスなので、初期費用もかからず無駄なく利用できます。さらにレンタル利用後は電話サポート、保険付帯、故障時即代替対応などのサポートを受けられるので、ロボット初心者の方でも安心して利用可能です。
SUPPOTの導入により重い荷物の運搬作業を削減できるため、人件費や労働コストの軽減、生産性の向上などに繋げることができます。
SUPPOTの利用を検討されている方は、ぜひ運営会社であるソミックトランスフォーメーションへお問い合わせください。
参考文献
建設産業の現状と課題(建設業就業者の現状)|国土交通省https://www.mlit.go.jp/common/001149561.pdf
農林水産省「農林業センサス」https://www.maff.go.jp/j/tokei/census/afc/index.html
物流を取り巻く動向と物流施策の現状についてhttps://www.mlit.go.jp/common/001354690.pdf
2022年版 ものづくり白書https://www.mhlw.go.jp/content/000944612.pdf

