人手不足や従業員の長時間労働などの課題解決に向けて、建設業界各社は業務にロボットを活用する「ロボティクストランスフォーメーション(RX)」に取り組んでいます。「自社でもロボティクス トランスフォーメーションを進めたい」と思っていても、具体的にどうしていいのか分からず、お困りの担当者の方もいるのではないでしょうか。
本記事では、建設業界におけるロボティク ストランスフォーメーションについて解説します。メリットや具体的な事例も紹介するので、人手不足や従業員の長時間労働などにお悩みの方は、ぜひご覧ください。
建設業のロボティクス トランスフォーメーション(RX)とは

建設業では、ロボットの活用について、各社が独自に研究・開発を行うだけでなく、技術連携や技術の相互利用が行われています。その動きは活発で、ロボティクス トランスフォーメーションは業界全体の動きといえるかもしれません。 そこで本項目では、ロボティクス トランスフォーメーションについて、「そもそもどういうものか」と「メリット」に分けて紹介します。
ロボティクス トランスフォーメーション(RX)とは?
ロボティクス トランスフォーメーション(RX)とは、ロボット変革(Robotics Transformation)を意味しており、ロボットを活用するDX(デジタル変革)のことです。具体的には、資材の運搬や施工といった、これまで人の手で行われていた業務をロボットに代替していきます。建設現場では、人手不足や熟練技能者の高齢化などが長年の課題です。そこで、ロボットに任せられる業務はロボットに任せることで、作業員の負担軽減や生産性向上などを目指します。近年、鹿島建設株式会社と株式会社竹中工務店、清水建設株式会社のゼネコン大手を中心にロボット・IoTアプリなどに関する研究開発を行う「建設RXコンソーシアム」を立ち上げるなど、業界全体で課題に取り組んでいます。
メリットは?
建設現場にロボティクス トランスフォーメーションを導入するメリットとしては、作業員の負担軽減と安全確保、生産性向上が挙げられます。 たとえば、搬送用ロボットを活用することで、作業員が重い荷物を持ち運ぶ必要がなくなるため、身体への負担が大幅に軽減できます。さらに重い荷物の持ち運びは腰を傷める原因になったり、誤って落とした際に大怪我の原因になったりしますが、ロボットを活用することで、作業員の安全を確保することも可能です。また、搬送用ロボットは人よりも多くの荷物を一気に移動させられるため、人の手で行うよりも生産性が向上します。プログラム通りに動くため、ミスの心配もありません。
国内建設業が抱える課題
国内建設業では、人手不足や長時間労働が長年の課題です。建設業者が生き残っていくためには、ロボット活用などにより、これらの課題に対応する必要があります。 本項目では、国内建設業が抱える課題、「人手不足」と「長時間労働」について詳しく紹介します。

人手不足
国内建設業では、人手不足が大きな課題です。国土交通省がまとめた「建設業及び建設工事従事者の現状」によると、建設業で働く労働者の約34%が55歳以上と高齢化が進んでいます。一方で、29歳以下の建設業で働く労働者は約11%です。日本建設業連合会の建設業デジタルハンドブックにある「建設業の現状」によると、新規学卒者の建設業への入職状況は2009年の2.9万人を底に増加に転じており、2021年には4.4万となっています。しかし、2025年には団塊の世代が75歳以上となるため、高齢者が大量離職する見込みです。今後、さらなる人手不足が懸念されます。
長時間労働
厚生労働省の「毎月勤労統計調査 令和3年分結果確報」によると、2021年の建設業の月間実労働時間は、165.3時間におよびます。調査産業計の総実労働時間は136.1時間のため、29.2時間多いことになります。 日本建設業連合会の建設業デジタルハンドブックにある「建設業の現状」によると、建設業の労働時間は減少傾向です。1988年に年間2,281時間だった年間労働時間は、2021年に2,032時間になりました。しかし、他産業と比較すると労働時間が長く、調査産業計よりも年間約320時間増の長時間労働です。
建設RXコンソーシアムへ参画しているゼネコンとロボット導入事例
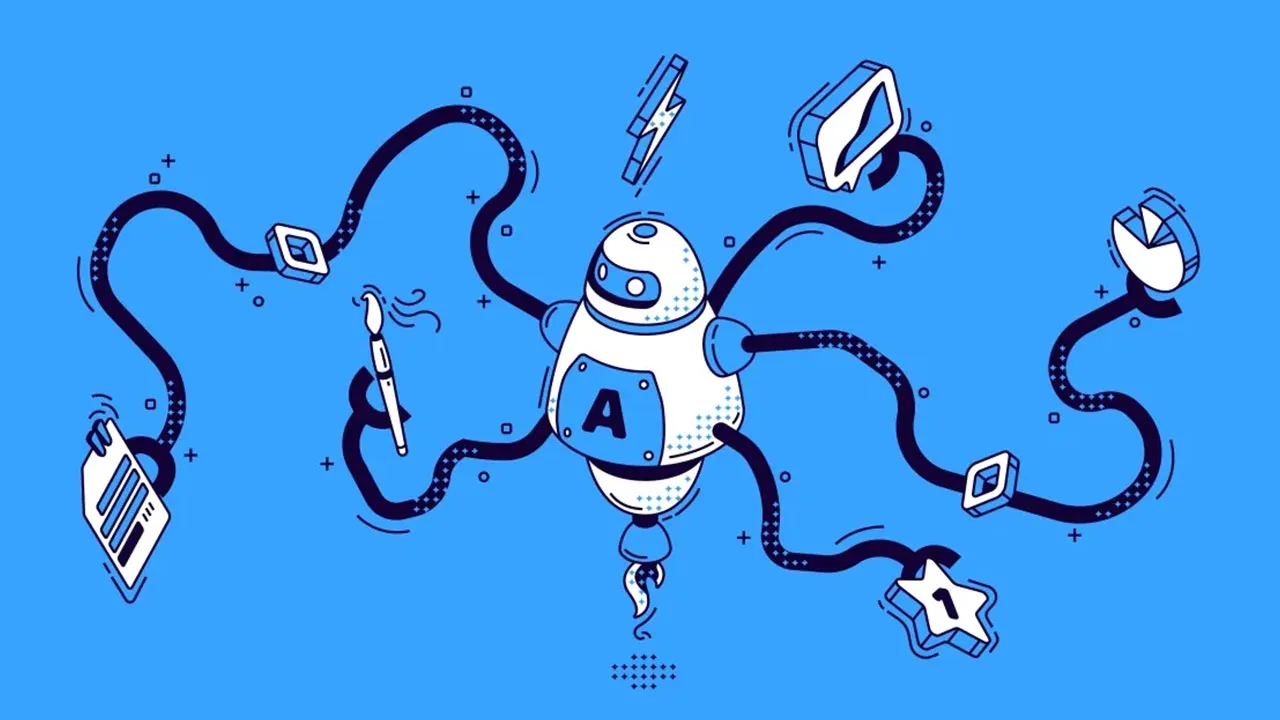
建設業界では、各社さまざまな用途でロボットが活用され、複数社で共同研究を行う「建設RXコンソーシアム」が立ち上がるなど、業界全体でロボティクス トランスフォーメーションに取り組んでいます。本項目では、「建設RXコンソーシアム」と建設RXコンソーシアムへ参画している「大林組と髙松建設のロボット導入事例」について紹介します。
建設RXコンソーシアムとは
「建設RXコンソーシアム」は、建設業界の人手不足の解消や生産性・安全性の向上、コスト削減といった課題解決を目的に設立された共同体。施工関連技術のうち、ロボット・IoTアプリ等に関する研究開発を複数社共同で行い、建設業界の課題を解決することで、建設業界全体の生産性や魅力の向上を目指しています。2021年9月、ゼネコン16社にて発足。2022年11月1日、大林組と高松建設が新たに正会員に、設備工事会社のダイダンや、測量機器メーカーのニコン・トリンブルなどが協力会員となったと発表され、正会員(ゼネコン)が27社、協力会員105社、合計132社にまで拡大しています。
大林組
大林組では、同じ階の搬送だけでなく、階をまたいだ垂直搬送を自動化するロジスティクスシステムを開発しています。担当者がウェブ上で搬送スケジュールや資材の搬送元、搬送先などを入力すると、無人での資材搬送が可能。システムが搬送ロボットや工事用エレベーター、カメラを統合的に管理しているため、階をまたいだ資材運搬も人の手を煩わせることなく、搬送元から指定のエリアに資材を運搬します。搬送指示工程スケジュールにあわせて約2週間分、エレベーター300往復分程度を設定可能。変更が生じた場合は指示を修正すると、システムが自動で搬送計画を組み替えるため、面倒な作業はほとんどありません。大林組は、資材搬送の労務を3割削減し、夜間の揚重作業の出来高を20%向上できるとしています。
髙松建設
髙松建設は、青木あすなろ建設株式会社、非破壊検査株式会社と3社合同で「壁面走行ロボットによる外壁点検システム」を開発しています。一般的な外壁検査方法は、壁面前面を打診し、音の異常の有無を検査員が聞いて診断しますが、診断の際に建物に足場を架設したり、ゴンドラやロープで上から検査員を吊ったりする必要があるため、コストや工期の負担、検査の診断精度などが問題でした。壁面走行ロボットは、壁面を吸着しながらローラーの回転により壁面を走行。搭載した打診測定器やカメラで検査を行います。建物オーナーの負担を軽減でき、診断結果をデータ化し、分析・蓄積することで高精度な診断も期待できます。足場を組んだり、ゴンドラなどで検査員を吊ったりする必要もないため、作業員の負担軽減にもつながるでしょう。
建設現場でロボットを導入するならSUPPOTがおすすめ
建設現場で、自律走行ロボットを導入するなら「SUPPOT」がおすすめです。
SUPPOTは、建設現場の資材運搬作業をサポートする作業支援ロボットをレンタルできるサービスです。SUPPOTでは遠隔操縦と作業者の自動追従や2D自動運転、最大100kgまでの重量物積載、悪路・傾斜の走行などが可能なロボットを用意。レンタルなので、購入よりも低コストで導入できる点も魅力です。 たとえば、コンクリート運搬をロボットで行うことにより、作業負担軽減と安全性向上、作業効率向上を実現した事例や照明器具を積載したロボットを作業者に自動追従させ、点検業務の効率化・省人化を実現した事例などがあります。建設現場での資材運搬の効率化や作業者の負担軽減、安全性向上などにお悩みの方は、作業支援ロボットレンタルサービス「SUPPOT」の導入をご検討ください。

まとめ
建設業界では、人手不足や熟練技能者の高齢化などが長年の課題です。人が行っている作業をロボットで代替していくロボティクス トランスフォーメーションは、これらの課題解決に役立つ有用な手段として注目を集めており、業界全体で取り組みを進めています。 人材不足や労働環境などに課題を抱えている企業は、簡単な作業からでも、ロボットの導入を検討してみてはいかがでしょうか。 「ロボットの種類がさまざまで、どれを選んでいいのかわからない」、という方におすすめなのが、作業支援ロボット「SUPPOT」レンタルサービスの利用です。 SUPPOTは1ヶ月からレンタル可能なサービスなので、初期費用もかからず無駄なく利用できます。さらにレンタル利用後は電話サポート、保険付帯、故障時即代替対応などのサポートを受けられるので、ロボット初心者の方でも安心して利用可能です。
SUPPOTの導入により重い荷物の運搬作業を削減できるため、人件費や労働コストの軽減、生産性の向上などに繋げることができます。 SUPPOTの利用を検討されている方は、ぜひ運営会社であるソミックトランスフォーメーションへお問い合わせください。
参考文献
建設労働|建設業の現状|日本建設業連合会https://www.nikkenren.com/publication/handbook/chart6-4/index.html
建設産業の現状と課題|国土交通省https://www.mlit.go.jp/common/001188729.pdf
最近の建設業を巡る状況について|国土交通省https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001493958.pdf
建設業及び建設工事従事者の現状|国土交通省https://www.mlit.go.jp/common/001180947.pdf
毎月勤労統計調査 令和3年分結果速報|厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/r03/21cr/dl/pdf21cr.pdf

